
どうも6児パパです。
会社や学校、大人も子供もストレス社会の現代で生きることは、時として心身の疲労やダメージを負うことも多々あります。
社会の中では、ありのままの自分ではいられず、調和や規律を守る為の自分へと変容しなければいけません。
その姿はまさに見えない鎧をまとうこと。
けれど、重荷を背負い続ければ、やがて現代病となりつつある”うつ病”の発症や、子供の人間形成に大きな影響を与えかねません。
そんな環境の中でも、唯一安らぎとなる場所。
それが”家庭”です。
今回は、大人や子供が社会の中で身にまとう”鎧”と、ストレス社会を生き抜く方法についてまとめました。
ストレス社会との向き合い方や心理的仕組み、子育てにおける家庭の在り方などを知ることができます。
重い鎧をまといストレス社会を生きていく

会社で上司・同僚、お客さんと向き合いながら仕事をする大人。
学校で先生・友達に囲まれながら勉強する子供。
家から一歩外に出れば、大人であれ、子供であれ、そこは全て社会です。
そんな社会の中では、人間関係・制約・責任・義務など、時に意に添わないことがあっても、忍耐と努力が必要になる場面があります。
社会の中では、”周囲の目”や他との調和、社会的制約などを守る為に、決してありのままの自分ではいられないこともあります。
その姿を例えるなら、社会で過ごす私たちは、常に”見えない鎧”をまとっている。
社会の中で身にまとう”見えない鎧”は、自己防衛や自己制御の役割を果たします(大人になるにつれて、鎧は”ステータス”の意味も加わり、地位や肩書を求めたがるのかもしれません)。
”見えない鎧”は、武将が身に付けるそれと同様に、刃を向けられた攻撃から身を守ることはできますが、ズッシリとした重みがあります。
鎧の重さはストレスへの耐久性や、楽観・悲観などの性格、人生経験によって形成された価値観など、様々な要素によって、個々に異なります。
例えば、楽観的な性格で、人間関係も円滑な環境の中で生きてきた経験があれば、”身にまとう鎧”は軽くてすみます。
けれど、ひとたび、経験したことのないストレスを感じる場面があれば、その鎧だけでは防ぎきることはできずに、心身を傷つけられてしまうことも。
逆に、悲観的な性格で、人間関係で悩み、人を信頼することが難しい経験をすれば、”身にまとう鎧”は重厚になります。
特に人生の中でトラウマ的な経験をした人にとっては、無意識に生まれる自己防衛本能から、ガチガチに固まった重厚な鎧を身にまとわざるえなくなることもあります。
普段から必要以上に気を張って、重い鎧をまとっている分、体が重みに耐えきれなくなって心身を壊すこともあるかもしれません。
特に働く30代は、仕事の中で様々なストレスを抱えることもありますよね。働く目的は、それぞれ違いますが、仕事をする理由は、人生を豊かにしたり、家族の幸せを望むからこそ頑張れる。けれど、心身を壊してしまっては元も子もありません。心身が壊れる前に、すぐにすべき対処が必要ですよ。
結論:家庭は休息の場所なんです

家庭=家とは、社会(学校や職場)で様々な心身の疲労やストレスを抱えながらも、ホッと一息つける安らぎの場所です。
刃を腰にそえ、鎧を身にまとった社会という戦場(決して争う場所ではありませんが)から離れ、家に帰れば、丸腰になって、ありのままの自分でいられる。
鎧を唯一おろせる安生の場所-それが家庭なんです。
気を張って、重い鎧を背負い、疲れ果てながら仕事や学校から帰った時。

「ただいま!!」
玄関に入った瞬間から重い鎧を下ろして、ありのままの自分になれる。
そこには、神経を使わなければならない相手や、わずらわしい環境はありません。
仕事から帰ったお父さんであれば・・・子供たちやママの顔を見て癒されたり、お風呂に入って身も心もスッキリしたり。
学校から帰った子供たちであれば・・・「おかえり」のママの優しい声に安心して、大好きな人と好きなことをして過ごす。
家庭は、社会の中で背負う重い鎧を下ろして、心身をリラックスし、エネルギーの活力となれる唯一無二の休息の場所なのです。
ストレス社会
大人の鎧

職場で感じるストレス・心身の疲労は、上記に述べた鎧が大きく関係しているように思います。
上司や同僚・顧客との対応の中で、どれだけプライベートで大変な状況があっても、笑顔を振りまきながら、調和を保たなければなりません。
しかし、重い鎧に心身が耐え切れなくなれば、あるいは鎧を貫いて大きなダメージを受けてしまえば、体を壊したり、うつ病を発症したり・・・。
加えて、様々な権利や主張が認められる現代においては、”言ったもん勝ち”のような風潮が高まり、自己主張の強い人が得をして、受け入れる人が損をする世の中と言えるかもしれません。
社会の中では、人は”見えない鎧”と共に、”見えない刃”も持っています。
自分の主張や価値観を相手に押し付けたり、時に相手を支配・攻撃する為に、言葉の刃をふりかざす。
こうした社会の中で生きていく為に、誰もが”鎧”を身にまとい、”刃”を腰に据えているのかもしれません。
それは本当にストレスがたまり、息苦しくさえ感じることもありますよね。
特に様々なタイプのある上司との向き合いに悩むことも多くあります。
「4つの上司の特徴と対策」について、詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。

鎧は環境によって変わっていく
けれど、”身にまとう鎧”は一生不変かと言えば、そうではありません。
上記の例をあげたように、最初はそうであっても、様々な人間関係や環境の中で、鎧の重さや形は変化します。
軽い鎧を身にまとう人であっても、誰かから裏切られたり、社会の中で、もまれていけば、重い鎧となることもあります。
重い鎧を身にまとう人であっても、人との優しさ・温かさに触れ、自分の中での葛藤を乗り越えることで、変化することができます。
人との信頼関係や自分に自信を持つことで、知らない間に鎧が軽くなることもあるのです。
”人の心の雪解け”
”自分の殻を破る”
こうした言葉の所以は、こういったことにあるのではないかと思います。
鎧の重量は、その人の自信によって変化するのではないかと思います。自分に自信を持つことができれば、まとう鎧は軽くなります。そして自信を持ちためには、他者より秀でたスキルが必要です。
子供の鎧

上述したように、社会の中で鎧をまとうことは、子供も同じ。
けれど、子供の場合は、置かれている社会が、大人ほど複雑ではない為に、このことが軽視されがちになります。
でもでも、子供も置かれている状況は同じなんです。
親や家族との関わりが主になる乳幼児期から、少しずつできることや、行動範囲も広がり、幼稚園・保育園、小学校と家族以外の人との関わりが増えていきます。
家で自由に思うままできていたことも、先生やお友達などと一緒に、目的をもった時間を過ごすときに、一定の規律や調和を守らなければならなくなります。
「先生の言うことを聞こう」=怒られるから
「我慢しよう」=友達と仲良くなりたいから
このようにして、子供も自制や周囲との調和の意識を覚えて、小さな鎧を身にまとうことになります。
鎧を身にまとうことで・・・
・我慢をしたり(大人=自分を律する)
・ルールを守ったり(大人=規則・法を守る)
・友達と仲良くしたり(大人=人間関係の調和を保つ)
・勉強したり(大人=仕事をする)
社会の中で鎧をまとうことは、決してネガティブなことだけではありません。
家庭から離れて、社会に出る上で「鎧を身にまとう」ことは、社会性を育む一歩と言えるからです。
子供の二面性を認識する
このようにして、子供は成長するごとに、良くも悪くも、「家の中での顔」と「外での顔」の二面性を持っていきます。
親としては、自分しか知らないと思っていた子供の表情に意外性を感じたり、時に寂しく思うこともあるかもしれませんが、そうした二面性も成長の証といえます。
ですので、「自分が見てる子供の姿が全て」という認識には注意が必要ですし、だからこそ、外での子供の様子を日頃から知る為に、家庭の中で密接な子供とのコミュニケーションが大切になるのです。
規則を守りながら一定の仕事(勉強)をこなして、時には上司(先生)に叱られることもあったり、同僚(クラスメート)との人間関係に悩むこともある。
子供が学校へ通うことは、大人が仕事に行くこととなんら変わりないことなのです。
だからこそ、子供が学校に行くことを当たり前と捉えてはいけません。

大人も子供も、会社・学校というそれぞれのフィールドで、様々な悩みやストレスを抱えながら、それでも頑張っています。
家族それぞれの頑張りを認めて、互いに敬意を持つことが大切なのです。

家庭が安らぎの場所でない過酷さ
外で気を張りながら、時として背負った重荷に心身共に疲れ果てたり、あるいはダメージを負った時、家という安住の地は心身の休息を与え、家族という唯一無二の存在は安らぎを与えれくれる。
この安住の地であるはずの家庭の中でさえ、鎧をまとわなければならないとしたらどうでしょう。
背負う重荷を下ろす場所はどこにもなく、ただただ疲れ果ててしまいますよね。
<大人の場合>
・夫婦がいがみ合って、要求や主張を一方的にする
・仕事や育児のしんどさや悩みを一人で抱える
・仕事の休みがなく、家で過ごす時間がない
<子供の場合>
・両親のケンカが絶えない
・家で一人ぼっちで過ごす
・塾や習い事ばかりで家での時間が少ない
・「勉強しなさい」とプレッシャーをかけられる
どれだけ裕福な生活ができたり、ステータス(大人=地位、子供=学力偏重)があったとしても、一時たりとも、心が安らぎ、心身共にリラックスして休息できる場所がなければ、心は豊かになれませんよね。
体験談:6児パパにとっての家庭
実際に6児パパも仕事を通して、やりがいや楽しさを感じる一方で、正直言って様々なストレスを抱えています。
職場での人間関係や対応など、様々なことに気を張って、調和や規律を保つために、重い鎧をまとってます。
時に打ちひしがれて、疲れ果てることもあります。
けれど、帰宅すると「おかえり」と駆け寄ってくれる愛する子供たちや妻の姿に安心感を抱いて、子供たちのお風呂、寝かしつけをしながらたくさんコミュニケーションをとる時間が、6児パパにとって安らぎの時間となっています。
休日は家族の食事を作ったり。
子供たちの勉強を教えたり、遊んだり。
労力としてエネルギーを使いますが、それ以上の癒しと活力を与えてくれます。

「あ~この時間の為に生きてるんだな」
どんなに苦しいことがあっても、帰る場所がある。
待っていてくれる人がいる。
愛おしい人との幸せな時間がある。
そう思えれば、どんなことだって乗り越えていける気がして、また明日に挑戦する充電と決意ができます。
家族って、家庭って、本当に大切だなって日々実感します☆

まとめ:愛する家族が待つ家庭が帰る場所
家庭は、社会で躍動する為の活力であり、時にストレスや様々なダメージを負ったとしても、癒しや安らぎを与えてくれます。
そこには唯一無二の愛する家族がいるからこそ、気を張ることなく、ありにままの自分でいられる。
愛する家族が待つ家庭という帰還できる場所があるからこそ、人は頑張れるし、幸せを実感できるのだと6児パパは確信します。
お父さん、お母さん、それぞれの役割を果たし、愛によって包まれる家庭こそ、幸せの源なんです。
とはいえ、家族への愛情も表現しなければ伝わりません。
家族の愛情についてはコチラ

お父さん・お母さんの家庭の中での役割について知りたい方はコチラをご覧ください。



最後までお読みいただき、ありがとうございます!!
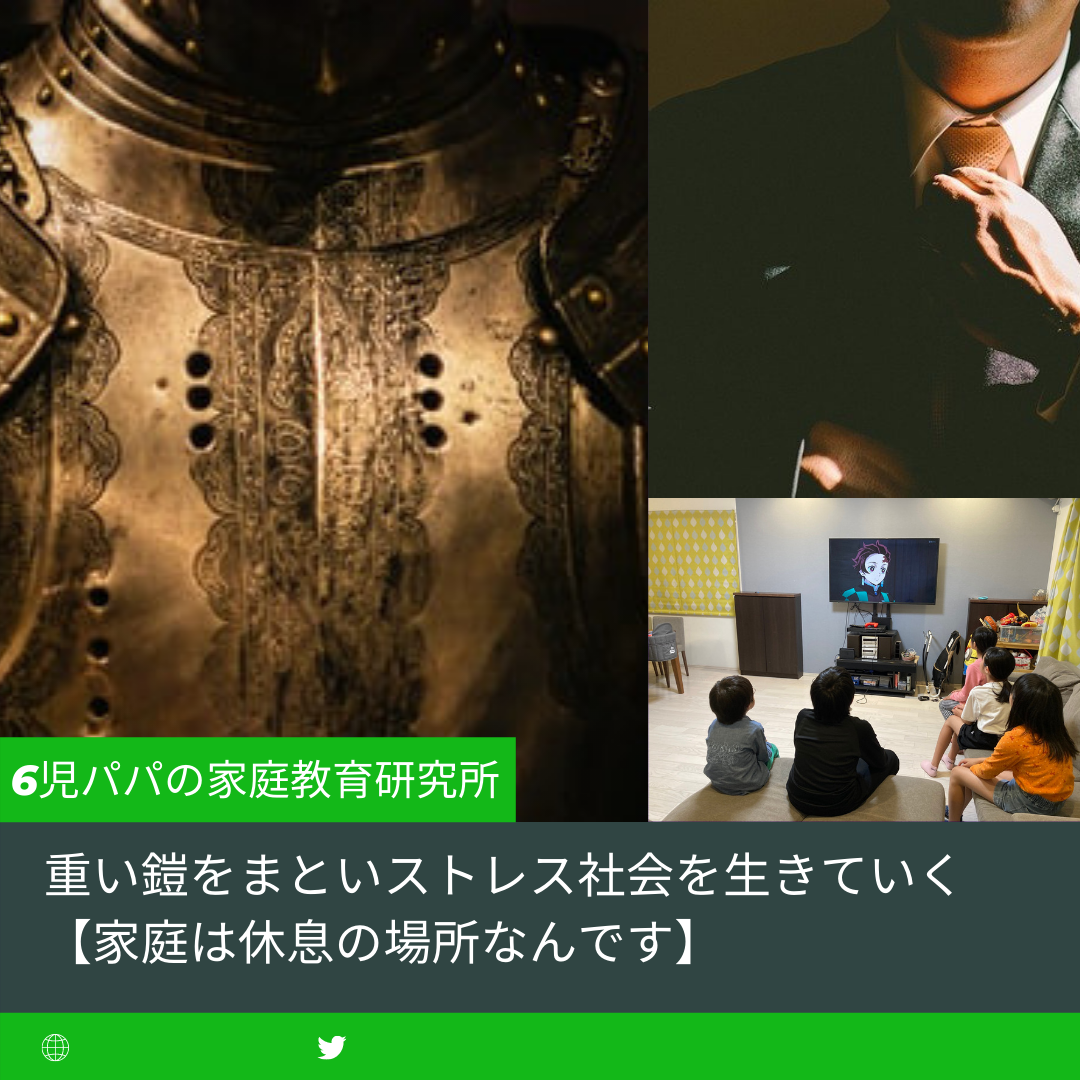


コメント