
どうも、6児パパです。
子育てには何かとお金がかかりますよね。
先日我が家でも6人の子供にかかる学習費総額を試算すると衝撃的な数字がたたきだされました。。。
大切な子どもの将来のために、親としては最大限の環境を整えてあげたいところ。
子供の将来を考えると、少しでも早く準備をはじめたい教育資金。
確実に準備する方法として貯蓄もありますが、保障や増やすことも可能な学資保険は、魅力的な方法だといえます。
子供にかかるお金の流れと、学資保険に加入する前に知っておきたい情報や、選ぶ際のポイントも解説していますので、最後までご覧いただければうれしいです。
6児パパの子供一人にかかるお金が衝撃的
文科省が平成30年に学習費調査を行った際の幼稚園から大学(公立・私立)の学習費総額をまとめたデータです。
| 総額 | 幼稚園(3年) | 小学校(6年) | 中学校(3年) | 高校(3年) | 大学(初年度のみ) | |
| 公立 | 2,308,505 | 223,647 | 321,281 | 488,397 | 457,380 | 817,800 |
| 私立 | 5,669,873 | 527,916 | 1,598,691 | 1,406,433 | 969,911 | 1,166,922 |
(出典:平成30年度子供の学習費調査 文部科学省)
*幼稚園・小学校・中学校・高校の学習費総額の内訳は【学校教育費・学校給食費・学校外活動費】です。
*公立欄の大学は国立大学を表します。
*私立の大学は文科系の大学の費用で算出しています。
公立学校で幼稚園から大学入学まで、子供一人につき約2300万円、私立にいたっては約5600万円もの学習費がかかるようです。
6児パパには13歳・12歳・10歳・8歳・5歳・0歳(2020年時点)の6人の子供がいるので、仮に6人全員が公立学校に進学したとしたら
2300万円×6人=1億3800万円
宝くじで1億円当たっても、まだ足りません(涙)
お金のことだけ考えれば、この先真っ暗になるところですが、子供の将来を思えば明るい未来しかありません。
だからこそ、親としては、子供が望む最適な環境を整えてあげたいですよね。
その為に大切なことが、堅実さと計画性なんです。
結論:子供の将来に大切な学資保険
家計の大きなウェイトを占める教育費ですが、小学校・中学校・高校・大学と子どもの成長に合わせて必要な費用も変わってきます。
だからこそ、子どもの将来をある程度予測して、早いうちから無理のない資金計画を立てておくことが大切です。
そのために力を発揮するのが、将来必要となる資金を確保するための学資保険です。
学資保険とは
学資保険とは、その名の通り、子どもの学資金(教育資金)を準備するための貯蓄型の保険のこと。
子どもの高校や大学入学等に必要な教育資金の準備を目的とし、積み立てと同様に毎月の保険料を支払い続けることで計画的に教育資金を作れる保険です。
貯蓄と学資保険の違い
貯蓄と学資保険の違いは次の通りです。
| 貯蓄 | 学資保険 |
| 積立期間に応じた積立金額 | 契約者(親)に万一のことがあった際に保険料の払い込みは免除となり、お祝い金・満期金を受け取ることができる |
今回は学資保険についてご紹介していきますが、貯蓄について詳しく知りたい方はコチラをご覧ください☆

学資保険の役割
教育資金の準備としての役割だけなら、貯蓄や株式、投資信託などで対応することも可能です。
けれど、多くの人が学資保険を選ぶ理由は、学資保険にしかない役割があるからです。
学資保険の役割を端的に言えば「子供の教育準備金を手堅く貯蓄して、親に万一のことがあった場合でも、子供の教育資金が準備できる」こと。
具体的には主に以下の二つの役割があります。
①教育資金準備
・子どもの成長に合わせた進学準備金や保険期間が受け取れる。
・満期を迎えた場合には、満期保険金を受け取ることができる。
・商品によっては、子どもの幼稚園入園や小学校入学などの節目の時期に、お祝い金としてまとまった給付金を受け取ることもできる。
②万が一の保障
・突然の事故などにより親(契約者)が亡くなった場合は、それ以降の保険料の払込が免除となり、保障がそのまま継続され学資金を受け取ることができる。
・医療保障などが付いた学資保険のタイプなら、子どもが病気やケガをした際に給付金が支給されたりするものもある。
・税制面で、支払った保険料は所得控除が適用されたり、お祝い金・満期保険金は一時所得として特別控除(50万円)が受けられる。
学資保険の仕組み
学資保険の仕組みは以下の手順の通りです。
①学資保険(会社)を選ぶ
②自分に合った学資保険商品(タイプ)を選択する
③毎月の保険料を支払う
④要所や節目の時期に保険が適用される
*医療特約があれば、家族の万が一の事態に保障を受けられる
*保険のタイプによっては、祝い金を大学在学中の毎年受け取ることができるものもある。
⑤保険金が満期になれば、満期保険金を受け取ることができる
*満期の時期については設定することができる

払い込みの方法
学資保険の保険料の払込には、次の3つの方法があります。
①月払
②年払や半年払
③全期間分をまとめて払い込む
*一時払(一度に保険料を払い込むこと)の場合は、払込が終わっているため、保険料の払込免除は適用されませんので注意が必要です。
学資保険を選ぶ際のポイント
学資保険を選ぶ際の主なポイントは「貯蓄型」と「保証型」のどちらを優先するかを選ぶこと。

学資保険をコツコツ積み立てて、子供が高校や大学に入学して、たくさんお金がかかる時期に受け取れる方が良い。
↓
貯蓄型
返戻率
返戻率とは、学資保険に加入して払い込む保険料の総額に対して、将来受け取れるお金(進学準備金や満期学資金)の総額がどれくらいあるかを表した数字で、通常はその割合をパーセントで示します。
<返戻率の計算式>
返戻率=(満期学資金+進学準備金)÷払込保険料総額×100
返戻率が100%を超えていれば、払い込んだ保険料より多くの学資金を受け取ることができます。
(例:払い込んだ保険料総額が100万円→満期学資金が110万円=返戻率は110%となります。)

子供や親に何が起こるか分からないから、教育資金もありつつ、万が一の備えたい。
↓
保障型
保障内容
医療特約には主に以下の4つがあります。
①「保険料払込免除」
契約者(親など)に万一のことがあった場合に保険料の払い込みが免除となる。
②「養育年金」
保険期間中に契約者(親など)が、死亡または所定の高度障害状態になった場合に保険期間満了まで受け取れる年金。
③「医療保障」・「死亡保障」
子供に対する保障として、入院などに備えることができる医療保障や万一の死亡保障が受けられる。
学資保険の注意点
学資保険の注意点は以下の2つになります。
①途中解約すると、受取金額が払った保険料以下になる。
途中解約しても解約返戻金は受け取れますが、払い込んだ保険料を下まわるケースが多いようなので、無理の無いプランニングが重要です。
②物価の変動に対応できない
子供が大学に進学するまでの長い期間に物価が上昇した際に、せっかく増えた資金もあまり意味を持たなくなるケースもあります。
月々の保険料の設定は計画的に
途中解約や収支(物価)の変動に備えて、学資保険を検討する際は、満期を迎えるまで払い込むことができる金額を考えることが大切です。
家計を圧迫することのないよう、月々の上限を決めるなど継続的に払い込める金額を設定しましょう。
学資保険はこんな人におススメ
コツコツ貯蓄するのが苦手なタイプの方にも学資保険はおすすめです。
銀行の預金は融通性が良いためについつい使い過ぎてしまう…そんな心配もなく、大切な教育資金を確実に準備することができるからです。
毎日の面倒な家計簿が億劫になって、さらに、趣味を諦めたり、食費をガマンしたりと、行動制限をして精神的に負荷をかけながら無理に支出を減らした結果、長続きせず。。。ガマンをしていた反動で余計に浪費してしまう・・・。
ダイエットに失敗して、お腹周りにゼイ肉がついてしまうのと同じように、家計の摂生や節約に失敗してしまえば、負債を抱えた”メタボ家計”になってしまう。

ドキッ!!
でも大丈夫♪心当たりのある方はコチラを参考にして脱メタボ家計を目指しましょう☆

加入は早いほうが良い
加入するタイミングは、早ければ早いほど良いと言われています。
それは、子どもの年齢が低いうちの方がその分、満期までの期間が長くなり保険料を抑えることができるため、家計の負担を抑えながら教育資金を準備することができるからです。
また、親(契約者)の年齢が高ければ高いほど保険料も高くなる為、できるだけ早めに加入することがおススメです。
加入時期について、一部の学資保険では、ご出産前に加入することが可能です。
ほとんどの学資保険は小学校入学までに加入が必要となっている為、全体的には、出産が無事終わり落ち着いてから、子供が1歳になるまでの間に加入する人が多いようです。
まずは無料で気軽に見積もりしよう
まずは無料で相談・見積もりができる保険ガーデンプレミアを利用してみましょう。
厳選された学資保険アドバイザーが、取り扱う10社以上の保険会社の中から最適なプランを紹介してくれて、自宅やWEB、店舗や喫茶店など都合の良い場所で、希望の時間に無料で何度でも相談してくれることができます。
期間限定で無料相談キャンペーンを実施しているので、今なら、もれなく全員に下記より1つをプレゼント中です♪

まとめ
<学資保険の特徴>
- 魅力的な貯蓄性が期待できる
- もしものための保障が受けられる
- 受け取るタイミングが設定できる
- 税制上のメリットがある
学資保険の最大の魅力は安心できる貯蓄性です。
学資金を受け取るタイミングが設定できるので、高額となりがちな大学入学時にまとまった満期学資金を受け取る他にも、子どもが中学校・高校・大学に入学するタイミングで、それぞれ進学準備金や満期学資金を受け取るなど、子どもの成長や家庭の状況に合わせて教育資金を準備することができます。
また、親が万一の事態が起こっても、保険料の払込免除の保障を受けられるという点も見逃せません。
貯蓄面だけを考えると、株式や投信信託といった選択肢もありますが、多くの人に学資保険が選ばれる理由は、こうした保険としての役割を備えているからと言えます。
大切な大切な子供の将来の為に、親としてできる最大限の準備と環境への備えをしてみてはいかがでしょう。
<今回ご紹介した学資保険無料見積もりサイト>
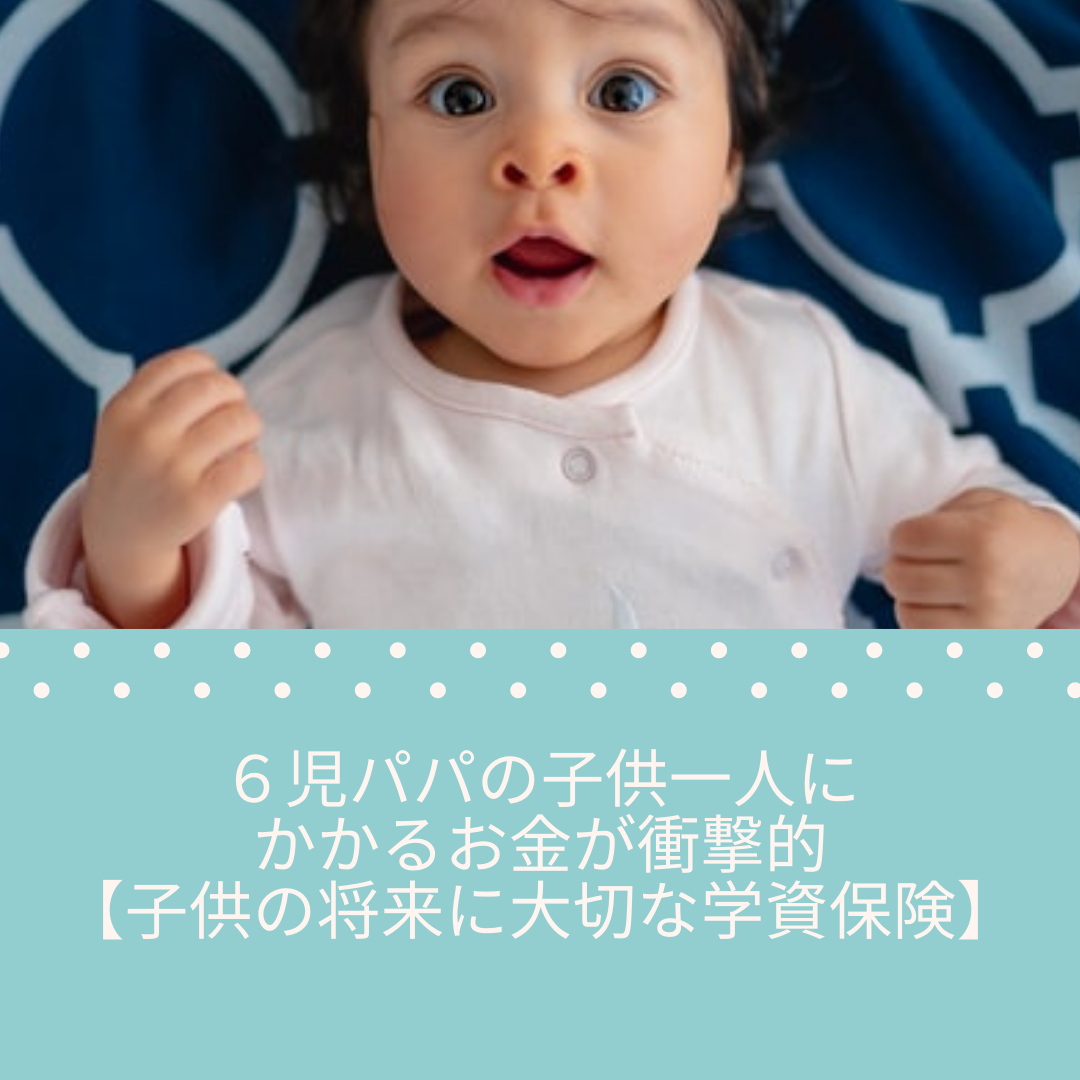
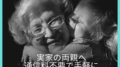

コメント