
・協調性の強い上司がいるから職場の雰囲気が良くて働きやすい。
・でも守るべき規律がゆるくなって、なあなあな関係になるのがな・・・。
・みんなで考えようっていう上司のスタンスも良いけど、もっとリーダーシップを発揮して欲しい。

組織を指揮・管理する”長”が協調性の強い上司ならば、自然と協力体制ができてきます。
ただし、良いところだけとは限りません。
言いたい事が言えなくなったり、色んなことがルーズになったりと、かえって組織の弱体化につながることもあります。
本記事では次のことを通して協調性の強い上司への問題解決の糸口をご紹介します
- 協調性の強い上司の5つの特徴を知る。
- ゆるい系なあなあ上司の対策は、あなた自身がリーダーシップを発揮すること。
- その為に4つのステップをサイクルする努力を行う。
- それでも難しい時は”新しい環境”に身を置く。
✔記事の信頼性
専業主婦のママと共に3男3女の子供を育てながら、「家族の幸せ」を求めて家庭教育を研究し、互いに敬意を抱く夫婦関係・愛情を注ぐ子育てを実践中。会社員として働く傍らで、大学で教育学を学び、ブログ・電子書籍販売・YouTube配信等を通して副収入を得る。(電子書籍の出版や、講演会依頼の実績も)
| 支配性 | 放任性 | 協調性 | 寛容性 |
| 指示・命令をして組織や人を支配したがるトップダウン型 | 大筋のレールすら明確に示さず、部下任せに運営する放置放任型 | 部下の意見を集約して、組織全体の力を活用する協力重視型 | 大筋のレールは築きながらも、指示・命令を行わず、部下に主体性を持たせる寛容柔軟型 |
 |
 |
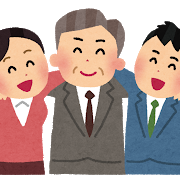 |
 |
6児パパオリジナル電子書籍がAmazon kindleから出版されました☆☆
ゆるい系なあなあ上司の対策とは

協調性の強い上司が職場にいることは、部下にとっては働きやすい職場になるかもしれません。
互いに協力し合って仕事をしたり、親睦を深める飲み会も多く、他の部署から見ても「仲が良いね」なんて羨ましがられることも。
けれど、そこにリーダーシップが伴わなければ、ただのゆるい系なあなあ上司になってしまいます。
ゆるい系なあなあ上司の特徴は、”根拠のない楽観主義”です。
たとえ職場として改善すべきことや、上司として対応を要することがあっても。
「みんな仲良くやっていこう」のスタンスだけでは、問題は解決せずに、どんどん大きくなるだけ。
加えて、ゆるい雰囲気が蔓延すると、会議での反対意見が出せなくなったり。
参加したくもない親睦会を断り辛くなることもあり。
真面目な社員にとっては、かえってストレスがかかってしまいます。
そんなゆるい系なあなあ上司の対策とは・・・。
結論:ゆるい系なあなあ上司の対策は”組織を引っ張るリーダーシップ”
ゆるい系なあなあ上司には、残念ながら決断力やリーダーシップが欠けていることがあります。
個と連携することが必要な組織では、メンバーを導くリーダーが必ず必要になります。
そうしたリーダー不在ともいえる状況の中にこそ、有能なリーダーの存在が必要になります。
もしあなたが、リーダー的役割を行える立場や能力を有するなら。
同僚と連携して、ゆるい系なあなあ上司に代わって組織を引っ張る役割を担う。
そうでなければ、リーダー的役割を担う人の神輿を担いで、リーダーシップを発揮してもらう。
そうすることで、ゆるい系なあなあ上司によって作られた良くも悪くも仲の良い組織に。
一定のメリハリを持った職場組織ができるのです。
職場のリーダーシップ・スキルについて詳しく知りたい方はビジネス・リーダーシップに必要なスキル【会社のインフルエンサーになって自己価値向上】をご覧ください。
ゆるい系なあなあ上司に代わってリーダーシップを発揮するステップ
①上司とのコミュニケーションを密にとり、肯定的な意見も否定的な意見も言い合える関係性を築く。
↓
②上司の承認を得た上で、組織をまとめる複数のチームリーダーを設ける。
↓
③リーダーが主体となって同僚と積極的なコミュニケーションをはかり、部下の本音や意見を吸い上げて、上司と再検討する。
↓
④ミーティングを何度も行い、それぞれが感じる不満や意見を出し合いながら、既存の仕事の在り方やルールを見直す環境を作る。
協調性の強い上司の組織の特色は、上司と部下の隔たりが少ないことです。
慣れ合いを恐れて、上司が指示・命令するタイプにシフトチェンジすれば、支配性が強化され、せっかく築いてきた協調性が失われてしまうことがあります。
そこでキーマンとなるのが、リーダーとなる部下の存在です。
「あえて厳しい意見を言うリーダー」「フォローするリーダー」など。
複数のリーダーを上司の承認の元で設けて、慣れ合いになりつつある組織の襟を正しつつ。
部下一人一人の本音を引き出せる環境を作りましょう。
最初は個別に部下の意見を聞きながら。
上司が同席のミーティングなどで、組織全体として意見を出し合うことで、不満や本音の膿を出し切り。
本当の意味で連帯感の強い組織作りを目指します。
とは言え、この過程をリーダーだけが行うにはあまりにも負担が大きすぎます。
その為に、上司からのバックアップを求め、密に連携をはかりながら。
最終的な判断や意見を上司に委ねることで、協調性とリーダーシップを併せ持った上司になってもらいましょう。
こうした地道な努力をしていく中で、自然とあなた自身のリーダーシップが身に付き。
本来上司が担うべき役割を積み重ねた経験が、あなたの将来に必ず役立つ時がやってきます。
さらに上昇志向を持つ方は会社員のコロナ大不況に備えた対策【副業・転職に強いビジネススキルとは】をご覧ください。
協調性の強い上司
<協調性の強い上司の事例>

おはよう!今日もみんなで力を合わせて頑張ろう!

うちの職場って、みんな仲が良いよなぁ
部下や周囲の協力を仰ぎ、みんなで力を合わせて一つの目的に向かう―そんな協調性の強い上司の元で仕事ができれば。
心理的な圧迫やストレスを感じず、理想的な職場と言えます。
こうした上司の居る職場では、連帯意識も高まり、和気あいあいとした雰囲気の中で業務ができます。
しかし、協調性を強く持って、皆で取り組める一方で。
組織の中では時に大事な場面で強いリーダーシップが求められることもあります。
そんな時ですら「みんなで協力して決めよう」なんていう姿は、悪い表現をすれば優柔不断に映ることもあります。
上司の4つのタイプは、部下の4つのタイプでもあります。
支配性の強い部下のもとでは、協調性だけでは、時に飲み込まれてしまうこともあります。
そうなれば上司の威厳は失われ、下手をすれば「居ても居なくても影響のない存在」になってしまうこともあるのではないでしょうか?

協調性の強い上司の特徴
「One for all,All for one」(1人はみんなのために、みんなはひとりのために)の精神ですね。
皆で分担しながら一つの目的に向かって取り組むことは、組織の運営に必要不可欠なことですよね。
上司がこの理念を大切にしていれば、自然とチームワークも組織力も高まっていきます。
一方で、組織は個性の集まりです。
献身的にチームの為に尽力する人だけでなく、積極的に自己主張をする”我の強い人”もいます。
協調性の高い組織では、時に”我の強い人”が煙たがれる傾向にあるかと思います。
しかし、新たな発想を生み出したり、幹の太い組織を作るには、こうした”我の強い人”も、組織には必要な人材になることがあります。
そうした時、ただ単に協調性が強いだけの上司では、残念ながら”我の強い人”が浮き。
組織に混乱を与え、結果としてチームの輪が乱れたり。
組織をまとめきれなくなってしまうことがあります。
協調性の強い上司にこそ、併せて様々な個性をまとめる強いリーダーシップが求められます。
一見すれば協調性の強い上司は、理想的な上司に見えますが。
いざという時にリーダーシップを発揮できるか否かが、紙一重となる上司と言えますね。
会社のリーダーになることは、会社の中のインフルエンサーになること。
会社の中のインフルエンサーになることについて詳しく知りたい方はコチラをご覧ください。
協調性の強い上司のメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
| ・組織としての一体感が生まれ、円満な人間関係が築ける | ・暗黙のルール(皆が行うサービス残業や行事参加)がいつのまにか生まれ、抵抗感がある部下に我慢が強いられる |
| ・皆で協力して目的を果たす達成感を感じられ、連帯感やモチベーションが向上する | ・組織内部での連帯感が高まり過ぎて、外部の人間(新入社員など)や新たなアイデアが受け入れ難くなる |
| ・上司、部下が同等の関係性でチームワークが高まり、楽しく仕事ができる | ・慣れ合いになりすぎて、組織としての本来の目的を見失うこともある。また上司の威厳が下がり、部下の管理・統制ができないことも。 |
部下としては最も働きやすい上司と言えますね。
周囲から見れば上司と部下の隔たりもなく、みんなが仲良く、チームワーク抜群の円満な組織に見えます。
また一つの目的に向かって、部下一人一人が役割を持って力を発揮することで。
部下のモチベーションやスキルが向上するようにも見えます。
ただし、協調性の強い上司の反面性は、あくまで”そう見える”ということです。
実際に組織の中では、様々な危険性が潜みます。
連帯感が高まり過ぎて、慣れ合いになり、指摘することや新たな発想を生み出すことを拒む風潮ができたり。
外部の人間や意見を受け入れ難い環境ができてしまいます。
加えて、組織の暗黙のルールが生まれ、それに馴染めない人は疎外感や抵抗感を抱くこともあるかもしれません。
逆に言えば協調性を持ったリーダーシップを身に付けられれば、どんな立場やどこの職場に行っても鬼に金棒といえる能力となります。
次の章では「協調性を高める方法」をご紹介します。
協調性を高める3つの方法

当然のことながら、人は1人では生きていくことはできません。
色んな人と協力し合って、組織も人生も成り立ちます。
その意味で人が生きる上で協調性はなくてはならない能力の一つです。
自分自身や、あるいは同僚・上司などに協調性が欠けていることで、悩む人の為に「協調性を高める方法」をご紹介します。
相手を尊重する
協調性を身につけるには、まずは他人の考えを認めることを意識しましょう。
協調性がない人は、自分の行動や考えを優先してしまいます。
その結果、自分と違う考えを持つ人のことを”間違い”と判断してしまいます。
しかし、人によって考え方は違います。
行動や考え方も人によって正解が違います。
まずは、自分と違う人は”間違い”という先入観を捨てて、相手の考え方を認めるようにしましょう。
人の話を傾聴する
ついつい自分の話ばかりをしてしまったり、人の話を遮ってしまうことも、協調性のない人の特徴です。
互いの考えを最後まで聞かないと分かり合うことはできません。
人と会話をするときには、相手の会話に口を挟まずに。
まずは相手の言葉をしっかりと聞いて、相手の考え方を認めるようにしましょう。
相手と比較しない
協調性のない人は、人の話しを聞きながらすぐに自分の意見と比較してしまいます。
そのことを繰り返していくうちに、自分のことが正しいと思い込んでしまう癖が身についています。
比較をする背景には、どこか自分に自信がなくて、比較対象を目の前において、自分が正しいと思い込みたがるという心理も働いているかもしれません。
こうした人は、これまで協調性のある人(自分を認めてくれる人)が側にいなかったのかもしれません。
けれど、分析はしても、比較する必要はまったくありません。
あなたはあなた、他人は他人なのです。
新しい環境に身を置く
どうすることもできなくなった時。
最後にして、一番確実な方法です。
最も大切なのは、自分の人生です。
社会で生きていく中では、どうやっても合わない人や組織はあります。
自分なりに精一杯、そこに適応する努力を続けた上で、それでもどうしようもない時は早めの決断が大切です。
心身の疲弊、年齢、経験など、あなたの人生にとって最良の選択をしましょう。
自分の人生には、誰も責任をとってくれません。
自分を守ること、人生を豊かにする環境は、あなた自身の手で築いていくしかないのです。
転職をお考えの方はコチラ
↓
まとめ:上司には4つのタイプがある
支配性の強い上司
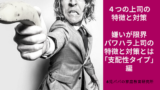
放任性の強い上司

寛容性の強い上司

まとめ:4つの上司の特徴と対策




コメント