2020年5月4日、政府は緊急事態宣言の対象地域を全国としたまま、5月31日まで延長することを決定しました。
不要不急の外出や休業の要請、学校の休校など国民の生活にが行われている中で、緊急事態宣言は、いつになったら終了となり、この事態が終息するのか。
その鍵となる、5月4日に発表された安倍首相の会見と政府の方針をまとめてみました。
緊急事態宣言の延長
政府は4日、新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を首相官邸で開きました。
その中で安倍首相は、記者会見で次のことを表明しました。
<緊急事態宣言の延長について>
<現状の感染状況や医療体制について>
<今後の方針について>
<経済的援助について>
「特定警戒都道府県」と「その他の地域」の外出自粛
<13の「特定警戒都道府県」>
・東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡
(最初に緊急事態宣言の対象となった7都府県)
+
・北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都
(後に緊急事態宣言の対象となった6都道府県)
↓
これまでと同様の制限
目標:「接触機会の8割削減」
(要請の対象外となる外出の例)
▽医療機関への通院
▽食料・医薬品・生活必需品の買い出し
▽必要な職場への出勤
▽屋外での運動や散歩など
「感染の拡大につながるおそれのある施設の使用制限の要請などを行う」
「社会経済や住民の生活・健康などへの影響を留意し、各都道府県知事が適切に判断する」
(例)
博物館、美術館、図書館、屋外の公園などは感染防止策を取ることを前提に、開放することも考えられる
「出勤者数の7割削減」の目標を掲げて、テレワークやローテーション勤務などの強力な推進を求める
<それ以外の34県>
↓
「3つの密」を避け、手洗いや人と人の距離の確保といった基本的な対策の継続など「新しい生活様式」を徹底することを前提に、制限の一部を緩和する方針
▽不要不急の帰省や旅行をはじめとした県外への移動
▽繁華街の接待を伴う飲食店などこれまでにクラスターが発生した場所への外出は引き続き、自粛を促す
それ以外の外出は、自粛を促す対象とはしていない
「感染拡大の防止や社会経済活動を維持する観点から、地域の実情に応じて各県が判断する」
・クラスターが多数発生している施設などは、使用制限の要請などを行うことを検討するよう求める
・クラスターの発生が見られない施設については、基本的な感染対策の徹底を強く働きかけるよう求める
・事業者などには業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取り組みを求める
「出勤者数の7割削減」の目標の対象からは外したうえで、テレワークや時差出勤など人との接触を減らす取り組みは続けることを求める
<全ての47都道府県対象>
▽クラスターが発生するおそれがあるもの
▽「3つの密」がある集まりは引き続き、開催の自粛の要請などを行う
▽特に全国的かつ大規模なものは感染リスクへの対応が整わない場合は、中止や延期など、慎重な対応を求める
*特定警戒都道府県以外の34県では、比較的少人数のイベントなどは「感染防止策を講じたうえで、リスクの態様に十分留意し適切に対応する」
「地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮したうえで、段階的に学校教育活動を再開し、児童・生徒が学ぶことができる環境を作っていく」
*これらの制限を行うにあたっては感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を図ることに留意する必要性を強調
「緊急事態宣言」対象地域の判断基準
緊急事態宣言の対象地域を判断する際の基準が新たに示されました。
判断基準は大きく次の2つに分けられます。
◇新たな感染者数などの水準
◇近隣都道府県の感染状況など
◇医師が必要と認めるPCR検査
◇院内感染の制御
◇救急医療などその他の一般医療への影響
◇医療機関の役割分担の明確化
◇患者の受け入れ先の調整機能
◇重症・重篤例の診療体制
◇病床の稼働状況や動向を迅速に把握・共有できる体制
◇重症患者から軽症患者まで病状に応じた迅速な対応を可能にする医療提供体制など
安倍晋三首相の記者会見の要旨(まとめ)
【緊急事態の延長の主な理由について】
→全国で毎日100人超が退院などで回復しているが、その水準を下回るまで新規感染者を減らす必要がある。
→各地への拡大を防ぐために地方への人の流れが生まれるようなことは避けなければならなず、全国を対象に延長する。
→有効な治療法やワクチンが確立されるまで感染防止の取り組みに終わりはない。
ある程度の長期戦を覚悟する必要がある。
【首相としての責任について】
→首相として責任を痛感。
中小・小規模事業者が厳しい経営環境に置かれ、さらに1カ月続ける判断をしなければならなかったことは断腸の思い。
【行動制限の緩和について】
→コロナの時代の新たな日常を一日も早くつくり上げなければならない。
ウイルスの存在を前提に、正しく恐れながら日常生活を取り戻していく。
→段階的に学校生活を取り戻し、今後2週間をめどに事業活動を本格化するための感染予防ガイドラインを策定する。
【追加経済対策について】
→早い人で8日から入金開始。
地方銀行や信金で実質無利子無担保の融資、納税や社会保険料の支払いも猶予するなどして事業と雇用を守り抜く。
→飲食店などの家賃負担軽減、雇用調整助成金のさらなる拡充、アルバイト学生への支援も与党の検討を踏まえ速やかに追加的な対策を講じる。
【医療・治療薬について】
→大都市圏を中心に徹底し、医療用ガウンや高性能マスクなどの医療防護具についても国内増産や輸入を一層強化する。
→日本で特例承認を求める申請があった新型コロナウイルスへの効果が期待される「レムデシビル」の速やかな承認手続きを進める。
「アビガン」も今月中の承認をめざす。
抗体検査を用いた疫学調査などを速やかに実施して、あらゆる手を尽くし次の流行へ万全の備えを固める1カ月にする。
【宣言解除について】
→地域ごとの感染者数の動向、医療提供体制の逼迫状況などを詳細に分析し、可能だと判断すれば期間満了を待たずに緊急事態を解除する。
まとめ
大型連休も緊急事態宣言の外出自粛を受けて、自宅で過ごすことを余儀なくされました。
感染状況や経済など、この先に多くの不安を抱える中での、今回の緊急事態宣言の延長。
しかし、政府が緊急事態宣言を延長する大きな理由として、医療体制の崩壊の懸念があるのではないかと思います。
外出の自粛などにより、国民の多くが今回の新型コロナウイルスへの危機感と、政府・自治体の生活の救済措置が整えられたことで、感染者の回復や、一時期に比べて感染者の減少がはかれたのかもしれません。
けれど、まだまだ予断を許さない状況があると見て、今回の緊急事態宣言の延長に踏み切ったのではないかと思います。
国民としては、政府の対応に様々な不満があるのも間違いありません。
けれど、今こそ、不平・不満をぐっと堪えて、一人一人が他者への思い遣りの心を持って感染予防に努め、今ある環境の中で楽しく活き活きと生きていくことが大切なのではないかと思います。
STAY HOME
自宅で過ごすことが、自身や他者の感染拡大を防ぐ最も有効な対策です。
とはいえ

退屈で何もすることがない・・・
そんな方はコチラをご覧ください♪♪


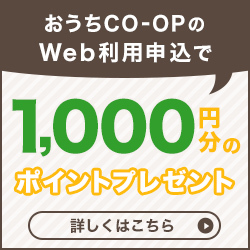





コメント