
・子供が乱暴な言葉を使う・・・。
・どうして子供はウソをついたり、ごまかそうとするんだろう。
・何度言っても、整理整頓ができない。
・子供の将来大丈夫かな??

子供の良くない部分って、親としては気になりますよね。
でもでも実は・・・子供の親の振舞いを見て子供は育つ。
逆に言えば、親が正しい言動、振舞いをすれば、子供は正しい習慣が身に付くんです。
本記事を通して次のことを得られます。
- 「子は親を映す鏡」の全文を解説して、子育ての教訓を知ることができる。
- 子供は親の姿を見て育つことを自覚して、まず親が変わることの大切さに気付くことができる。
- 正しい習慣を身に付ければ、子供は変わることができる。
✔記事の内容
・ことわざ”子は親を映す鏡”
・「子は親を映す鏡」解説
・子供は親の姿を見て育つ
・鏡の前こそ襟を整える
・6児パパの子育て
・現実の子育て
①子供に精一杯愛情をかけて育てる
②親が成長する姿を子供にみせる
・結論:正しい習慣で子供は変わる
✔記事の信頼性
専業主婦のママと共に3男3女の子供を育てながら、「家族の幸せ」を求めて家庭教育を研究し、互いに敬意を抱く夫婦関係・愛情を注ぐ子育てを実践中。会社員として働く傍らで、大学で教育学を学び、ブログ・電子書籍販売・YouTube配信等を通して副収入を得る。(電子書籍の出版や、講演会依頼の実績も)
6児パパの子育て風景を知りたい方はコチラ。
ことわざ”子は親を映す鏡”
子供は親の姿を見て育つことを表す言葉としてよく聞く言葉・・・
「子は親の鏡」
ドロシー・ロー・ノルト
アメリカの女性教育者ドロシー・ロー・ノルトによって書かれた詩なんです。

1954年に生まれた詩「子は親の鏡」は37ヵ国語に翻訳され、時代の流れに応じ、作者によって修正が加えられました。
「子は親の鏡」の全文は以下になります。
「子は親の鏡」
けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる
とげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる
不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる
「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもはみじめな気持ちになる
子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる
親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる
叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう
励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる
広い心で接すれば、キレる子にはならない
誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ
愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ
認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる
見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる
分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ
親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る
子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ
やさしく、思いやりをもって育てれば、子どもは、やさしい子に育つ
守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ
和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世はいいところだと思えるようになる
「子供が育つ魔法の言葉」(ドロシー・ロー・ノルト、レイチャル・ハリス共著、石井千春訳、PHP研究所)より引用
子どもは親を手本にして育ち、 毎日の生活で目にする親の姿こそが、子どもに最も影響力を持つことをあらわした詩です。
書店にあるようなどんなベストセラーの子育て本に出てくる言葉よりも。。。
「子は親の鏡」の詩が6児パパにとって最も心に響く格言だと思っています。
「子は親を映す鏡」の意味
「子は親の鏡」の前半部分は、親のネガティブな態度が及ぼす子供の影響について現わされています。
けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる
とげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる
不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる
「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもはみじめな気持ちになる
子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる
親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる
叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう

親が子供の心身を傷つけたり、子供の自尊心を損なう関わりをしていくことで・・・子供は自分に自信が持てなくなって、卑屈で時に乱暴な人間に育ってしまうこともある。
「子は親の鏡」の後半部分では、親のポジティブな態度が与える子供の影響について現わされています。
励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる
広い心で接すれば、キレる子にはならない
誉めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ
愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ
認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる
見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる
分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ
親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る
子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ
やさしく、思いやりをもって育てれば、子どもは、やさしい子に育つ
守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ

親が子供を広い心で包み込み、子供の自尊心を大切にする姿勢を示すことで・・・子供は自分に自信を持って、強く優しい人間に育っていく。
そして、 「子は親の鏡」の最後には、子供が育っていく家庭の大切さを説いて締めています。
和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世はいいところだと思えるようになる

家庭の中で子供が愛情をかけられながら、いつも笑顔で育っていけば、子供は”生きること”が楽しく感じられます。
”生きること”を楽しく感じられる人生になれば、社会の中で人との関わりを自ら求めたり、いろんなことに興味や関心を抱いて夢を抱くこともできます。
たくさんの人に囲まれて、やりたいことに挑戦し、自己実現できることで、子供は人生の幸せ・豊かさを持った人間になることができるのです。
子供は親の姿を見て育つ
「子は親の鏡」という言葉は、親が子供に接する態度によって、子供の将来(人間形成)に大きな影響を与えるという意味が込められていますが。。。
6児パパは「鏡」というフレーズに着目すると、もう一つの意味が込められているように感じます。
それは・・・
目の前の子供の姿は、親の姿
鏡の前に立てば、自分の姿が映ります。
ニコッと笑えば、鏡に映る自分も笑顔になるし・・・
ムスッとすれば、鏡に映る自分も怖い顔になる・・・
このことを「子は親の鏡」にあてはめれば
鏡の前に立つ実像=親
鏡にうつる虚像=子供
となります。
実像である親がイライラした姿で子供と関われば、子供の気性は荒くなり反発する姿になってしまうことがある。
逆に親が穏やかな姿で子育と関われば、子供の気性は穏やかになり優しい姿になる。
それは、情緒だけでなく、私生活についても同じです。
・片付けができない
・乱暴な言葉や態度をとる
・物を大切にできない
・社会的ルールが守れない
・一方的に自己主張ばかりする
親が子供の姿を見て”デキていない”と感じられる時、その背景には親の”デキていない”姿があるかもしれません。
なぜなら「子供は親を映す鏡」だからです。
鏡の前こそ襟を整える
出かける時に、鏡の前で何をしますか?
無造作になった襟を正して、身なりを整えますよね。
子育ても同じなんです。
鏡となる子供の前こそ、親として子供の手本や良い影響を与える存在としての振舞いを意識する必要があります。
6児パパの子育て
特に乳幼児期(0歳~2歳)は、言葉が話せない分、目(視覚)からの情報で子供は多くのことを学びます。
言葉を覚える幼児期(3歳~5歳)には耳(聴覚)からの情報で多くを吸収します。
幼い子供は目の前の光景から目と耳で様々なことを吸収し、模倣(同じように行う)する習性があるのです。
我が家でも、6人の子供の上の兄弟がケンカをして大きな声を出したり、ふざけて物を投げようとすると、たとえ”するフリ”で寸止めしても、小さな子供は、その姿から学習して実行してしまうことがあります。
子供が1人目の時は親が密接に子供と関わり合うことができましたが、子供が増えるごとに、常にそばにいられることが難しくなります。
そうした時に、子供が走り回ったり、兄弟ゲンカをしたり、事故や悪影響につながりそうな場面があると、すぐには駆けつけられない分、”声”で止めざる得ないことがあります。
出したくなくても親が大きな声を出さざる得ない状況となり、そんな親や兄弟の姿を見て、小さな子供は知らず知らずのうちに影響されてしまう・・・。
同じ5歳頃の姿を比較すると、余裕をもって子育てできていた頃の長男の気性は穏やかでしたが、5番目の下の子供の気性は少しあらあらしくなっていたように思います。(その分、他の子供にはない”たくましさ”を身に付けています)
現実の子育て
”子供と接する時は、親は心に余裕を持って、常に穏やかに優しく子供と接するようにしましょう”
そんな子育て番組で専門家が言っているコメントのような子育てを、現実の生活で常に行うことは、ハッキリ言って理想論です。
「子は親を映す鏡」を意識することは大切ですが、親も成長途上の人間。
他人の手本となるような完璧な人間などいません。
”だから子供に怒鳴っても仕方ないじゃん”っというわけにはいきませんが、6人の子供を育てる中で「子は親を映す鏡」の子育てをする上で大切なことは、次の2つだと実感しました。
①子供に精一杯愛情をかけて子育てする。
②親が成長する姿を子供にみせる。
子供に精一杯愛情をかけて子育てする
6児パパは講演会などで、よく子育てを「ぬか漬け」に例えます。
ぬか漬けをする為には、生ぬかや調味料が必要です。
どれだけ高価な調味料を使っても、ぬかが少なければ、水っぽくなって良いぬか漬けはできません。
子育てにおける”ぬか”は愛情です。
子供と過ごすどんな場面においても、根底には愛情が必要で、精一杯愛情をかけて子育てすることが大切なのです。
そこに目先の結果や親の要望を求めてはいけません。
ただただ毎日同じことの繰り返しのように見える子育てであっても、そうした親の姿から子供は様々なことを吸収して「子は親の鏡」の子育てができるのです。
家族へ愛情表現については家庭の幸せを左右する愛情表現の方法とは!行動しなきゃ伝わらないをご覧ください☆
親が成長する姿を子供に見せる
人生はいくつになっても学び多いものです。
親という立場には、子供が誕生した瞬間になれますが、”良き親”には、そう簡単になれません。
子育ての中で、試行錯誤し、悩み、時に自己嫌悪に陥ったり、涙を流すほど打ちのめされる経験を経て、親もまた様々なことを学び、人間として成長できるのです。
完璧な親や人間なんて、どこにもいません。
また、子育てに正解などありません。
なぜなら、親が向き合う相手は、様々な感性を持った一人の人間(子供)であり、その個性や育つ環境は十人十色に異なるからです。
大切なことは目の前の子供のことをよく知り、そんな子供が豊かに成長できる関わりや環境を築くことです。
子育てのスペシャリストになる必要はありません。
我が子を誰よりも知り、愛情をかける”子供のスペシャリスト”になることを目指しましょう!!
結論:正しい習慣で子供は変わる
「子は親の鏡」
子どもは親を手本にして育ち、 毎日の生活で目にするの親の姿こそが、子どもに最も影響力を持つ存在。
親のネガティブな態度が及ぼす子供の影響。
親のポジティブな態度が与える子供の影響。
そして、子供が育っていく家庭の大切さ。
「子は親を映す鏡」を肝に銘じて、子供の前こそ襟を正すことが大切です。
とはいえ現実の子育てでは、理想論だけではどうにもならないこともあります。
「子は親を映す鏡」を意識することは大切ですが、親も成長途上の人間。
だからこそ「子供に精一杯愛情をかけて子育てする」「親が成長する姿を子供にみせる」ことを繰り返し行いながら、親もまた子供と共に成長する姿が大切です。
どのような家庭環境で子供が育つか-。
家庭環境が子供の将来を左右するのです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
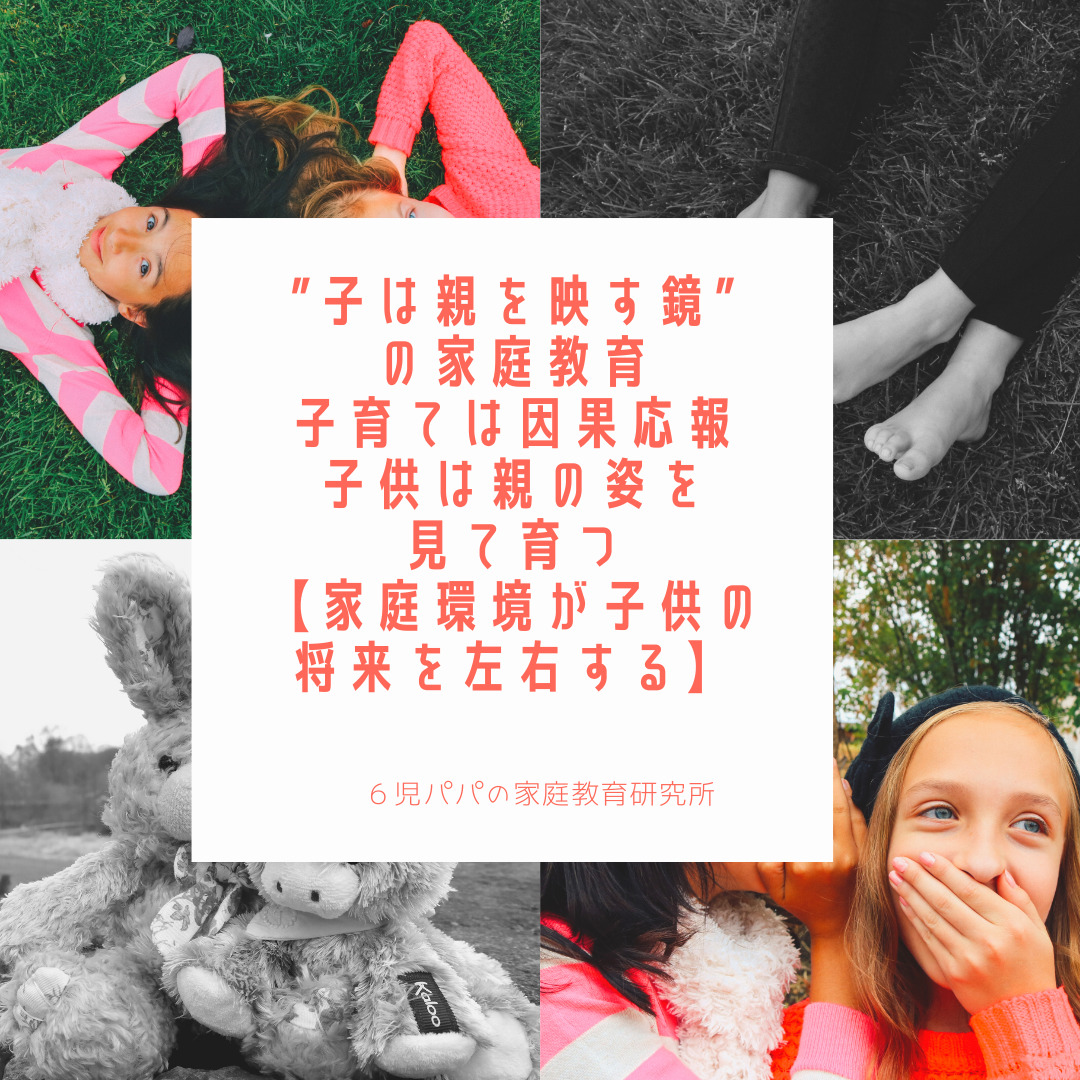


コメント