
・なんでもかんでも部下任せに仕事を振ってくる上司に疲れた。
・無責任に仕事を丸投げしてくる。
・頼りない上司にこの先不安になってくる。

次々と押し付けられる仕事の山。
明確な指示もなく、なんでもかんでも部下任せ。
放任主義の丸投げ無責任上司もまた、大きな悩みの種です。
本記事では次のことを通して「放任性の強い上司」との向き合い方・問題解決の糸口をご紹介します。
- パワハラ上司の特徴を5つの特徴を知る。
- パワハラ上司の対策は、上司に過度な期待をもたないこと。
- その上で4つのステップをサイクルする努力を行う。
- それでも難しい時は必殺”他力本願”。
✔記事の信頼性
専業主婦のママと共に3男3女の子供を育てながら、「家族の幸せ」を求めて家庭教育を研究し、互いに敬意を抱く夫婦関係・愛情を注ぐ子育てを実践中。会社員として働く傍らで、大学で教育学を学び、ブログ・電子書籍販売・YouTube配信等を通して副収入を得る。(電子書籍の出版や、講演会依頼の実績も)
| 支配性 | 放任性 | 協調性 | 寛容性 |
| 指示・命令をして組織や人を支配したがるトップダウン型 | 大筋のレールすら明確に示さず、部下任せに運営する放置放任型 | 部下の意見を集約して、組織全体の力を活用する協力重視型 | 大筋のレールは築きながらも、指示・命令を行わず、部下に主体性を持たせる寛容柔軟型 |
 |
 |
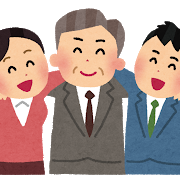 |
 |
6児パパオリジナル電子書籍がAmazon kindleから出版されました☆☆
無責任丸投げ:部下任せ頼りない上司の対策とは
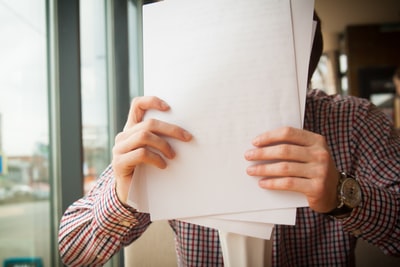
自分では何もやろうとせず、部下に仕事を丸投げ。
いざという時も頼りない放任上司には、やる気や責任感が欠けていることが多くあります。
その分、部下にかかる負担は甚大なものとなり、気力も体力もクタクタ・・・。
「もっと仕事をして欲しい」
そんな淡い期待を抱けば抱くほど、期待は失望へと変わり、更なる境地へ陥ってしまうことも。
そんな放任上司の対策とは・・・
結論:放任上司の対策は”上司に過度な期待を持たないこと”
放任上司の最大の特徴は自分に甘いということ。
自分に甘い放任上司は、自分の役割すらも無責任に他者へ丸投げをして、会社組織を指揮・統括するリーダーシップも乏しい。
そんな放任上司への対策の根本は、上司に過度な期待を持たないことです。
期待を抱き続ける限り、不満やフラストレーションはたまっていくばかり。
部下一人一人が「ここのリーダーは自分だ」という意気込みで業務をこなしていくことが大切です。
努力を続けていけば、おのずと同僚や他の上司からの評価は高まります。
そして自分が昇進した時には、放任性の強い上司を反面教師にしながら、能力の高い上司になることも可能になるんです。

放任上司に過度な期待をもたない為のステップ

①上司からの指示を期待せず、チーム(組織)として業務を遂行することを心がける。
↓
②膨大な仕事量も、同僚と連携して、計画的に分担し合いながら、効率的に業務をこなしていくことを目指す。
↓
③同僚とのコミュニケーションや後輩の指導を積極的に行い、リーダーシップを磨く。
↓
④自分にしかできないノウハウやスキルを業務で発揮しながら、仕事の成果をあげることで、周囲からの評価・実績が認められ同僚からリーダーとして認知される
①上司に期待しないチームワーク
部下任せの頼りない放任上司への期待は捨てましょう。
とはいえ、本来上司がすべき業務もこなしていくわけですから仕事量は膨大です。
だからこそ同僚同士で連携しながら、組織の力を発揮することが大切です。
同じような環境で仕事を強いられる同僚と協力し合いながらチームワークで業務をこなす。
最初は大変かもしれませんが、月日が経てば、自然と連帯意識が深まり、自分自身の能力も向上していきます。
②計画的・効率的に業務をこなす
膨大な仕事量だからこそ、計画的かつ効率的に業務をこなしていくことが大切です。
上司が業務に関与しないという放任上司の利点を生かして。
新たな手法や画期的なアイデアを取り入れ。
業務完了への経過を逆算した計画を立てながら、役割分担をして効率的に業務を進めていくことを目指します。
そうした努力によって得た経験やスキルは、今後、必ず活かされる時がきます。
③リーダーシップを磨く
チームワークで業務を進めていくためには、誰かが中心的立場となって指揮をとらなければなりません。
大変な役割ではありますが、あえて率先して自らその役割を担って、同僚とのコミュニケーションや後輩への指導を積極的に行いましょう。
頼りない放任上司の元で仕事をするというこの不遇の時をチャンスに変えて。
後に昇進して組織を任される立場になった時をイメージしてリーダーシップを磨きましょう。
「自信が持てない」「できない」
そんな弱気な自分が出てきたときは、自己マインドコントロールです。

④実績を重ねてチームのリーダーになる
頼りない放任上司には、組織の秩序として、報・連・相だけはしておきながらも。
チームの中心に立って、次々と業務上の実績を積み重ねていきましょう。
そうした積み重ねによって、周囲からは自然と、あなたがリーダーとして認知されます。
同僚や他の上司から認められることで、会社組織の中で影響力を持ったインフルエンサーになることができます。
会社の中のインフルエンサーについて詳しく知りたい方はビジネス・リーダーシップに必要なスキル【会社のインフルエンサーになって自己価値向上】をご覧ください。
放任性の強い上司
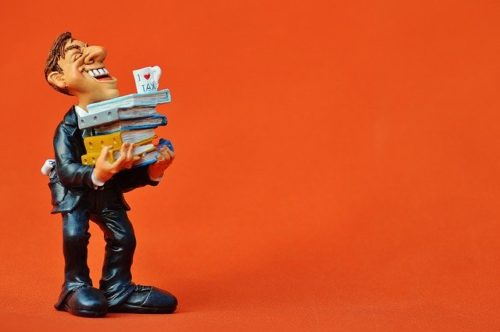
支配性の強い上司と真逆のタイプです。
無責任に仕事を丸投げして、指示があいまいな頼りない上司は、放任性の強い上司といえます。
上司でありながら、何をしていいかわからない、あるいは自分が負担になりたくないから、部下に仕事を放りなげる。
プライドが高く、自信過剰気味の支配性の強い上司とは真逆で、自信がない人がこのタイプに多いように思います。
<放任性の強い上司の事例>
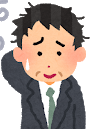
とりあえず、やっといて

とりあえずって・・・何をどうすればいいんだよ
放任性の強い上司が属する組織は、ゆる~い雰囲気が組織全体を包みます。
割り切りビジネスパーソン(時間内に働いて給料をもらうことだけを目的とする人)にとっては、最善の環境と言えるかもしれません。
一方で、組織としては見えない危機が常につきまとっていると言えます。
ゆる~い組織の中で、規律や指示があいまいな為、時に人間関係の崩壊や業務上の大きな事故などの発生が隣り合わせになる事があります。
それでもこうした放任性の強い上司の居る組織が成り立つには、大抵凄腕のナンバー2が居る事が多いです。
こうした背景から見ても、組織というのは一人のリーダー(上司)によってではなく、構成するメンバー全員の力によって成り立つことがわかりますよね。
放任性の強い上司の特徴
明確な指示もなく、いわばノ―プランの状態から部下に丸投げ状態。
組織を統括したり、管理する能力が自分にないことを自覚しているならまだしも、タチが悪いのが放任していることを正当化するタイプ。
そんなタイプは「部下に主体性をもたせるために、あえて・・・」なんて、放任していることへの理由付けを作ろうとします。
そのわりに、変な所では強いこだわりがあって、現場がどんな状況であってもマイペース(悪く言えば自己中)で、偏った業務だけをこなそうとする。
性格的には、自分に甘く、時間や約束にルーズなことが多い為に、業務の中で伝達したことすら忘れてしまうことも、しばしば。
『不器用な人なんだろうな』と部下が落とし所を探していると、幹部の前では一転して、あたかも自分が管理・統括して業務をしているパフォーマンスをみせちゃったりすることも。
部下としてはツッコミどころ満載の上司のタイプですね。
放任性の強い上司のメリットとデメリット
| メリット | デメリット |
| ・部下の力がつく | ・何をどうすればいいかわからず、組織は混乱して、部下の負担が多くなる |
| ・対等な立場同士が意見をすり合わせれば、現場視点のよりよい組織ができることもある | ・リーダーが不在な為、組織の秩序やルールがあいまいになり、第二のボス(支配性タイプ)を生み出す |
| ・管理、責任の在り方を共有して、部下の危機管理能力が育つ | ・管理、責任の所在があいまいで、大きな事故が起きる危険性が高まる |
部下としては一番困ってしまうタイプの上司と言えます。
ただ支配性とは逆に、放任性をプラスに捉えれば、大変ではあるけれど、部下がある程度の権厳を得て、自由に取り組むことができるのでフットワークの軽い組織ができます。
加えて、部下が自ら考え行動するような有能な方々であれば、本来上司が遂行すべき業務も同時に担う為に、通常では経験できないような管理・統括の力も身につけることができ、部下の力は著しく向上させることもできます。(大変だけどね。。。)
その反面、組織の中で人間関係や業務上の秩序・ルールがあいまいになってしまう為、先に述べたような事故の危険性や、部下の横暴も野放しにしてしまうことがあります。
その結果、支配性の強い部下が組織の中での実質的な長となり、パワハラなどで人間関係の崩壊につながっていく危険性もあります。(憶測ではありますが、教員いじめ問題があった須磨の小学校は、まさに典型的なこの例と言えるのではないでしょうか?)
劣悪な環境から脱却する為には、経済的な担保を確保することが大切です

限界突破の最後の策”他力本願”

とはいえ人間には限界があります。
「こんな上司だから仕方ない」と割り切って、膨大な仕事量や理不尽な業務を行っても、体力的・精神的・時間的・能力的に限界が出てくることもあります。
精一杯努力している中で、限界が見えてきたのなら、残る方策は一つ。
「他力本願」です。
決して聞き心地の良い響きではありませんが、自分の力ではどうしようもなくなった時、頼れるのは強い影響力を持った他者の力です。
別の上司に相談する
放任性の強い上司以外に、信頼できる上司がいれば相談しましょう。
社会人の先輩として、会社の上司として的確なアドバイスがもらえるかもしれません。
また何らかの形で、放任性の強い上司にはたらきかけてくれ事も期待したいですね。
けれど、相談する上司の人選を間違えば、かえって風向きが悪くこともあるので、慎重な判断が必要になります。

第3者機関に相談する
最近は組織もコンプライアンスや労働規則の問題から第3者評価を設けているところが多くあります。
文字通り会社とかけ離れた第3者機関が組織の業務・環境改善の為に、会社から依頼(または外部からの要請)を受けて、現場で働く人や組織にヒアリングをして改善案を出してくれます。
もしも、あなたが働く場所でそんな機会があれば、ありのままを相談しましょう。
あるいは労働体制(超過勤務や人権侵害など)に関して、どうしようもない不満があれば、各地域に設置されている労働基準監督署へ相談することも。
ただし、これらも第3者機関の対応によっては、気が付けばヒアリングしたことが筒抜けになってしまっていたなんて事態も考えられないこともないので、それ相応の覚悟も必要かもしれません。
転職する
どうすることもできなくなった時。
最後にして、一番確実な方法です。
最も大切なのは、自分の人生です。
社会で生きていく中では、どうやっても合わない人や組織はあります。
自分なりに精一杯、そこに適応する努力を続けた上で、それでもどうしようもない時は早めの決断が大切です。
心身の疲弊、年齢、経験など、あなたの人生にとって最良の選択をしましょう。
自分の人生には、誰も責任をとってくれません。
自分を守ること、人生を豊かにする環境は、あなた自身の手で築いていくしかないのです。

まとめ:上司には4つのタイプがある
支配性の強い上司
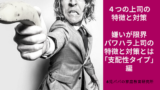
協調性の強い上司

寛容性の強い上司

まとめ:4つの上司の特徴と対策

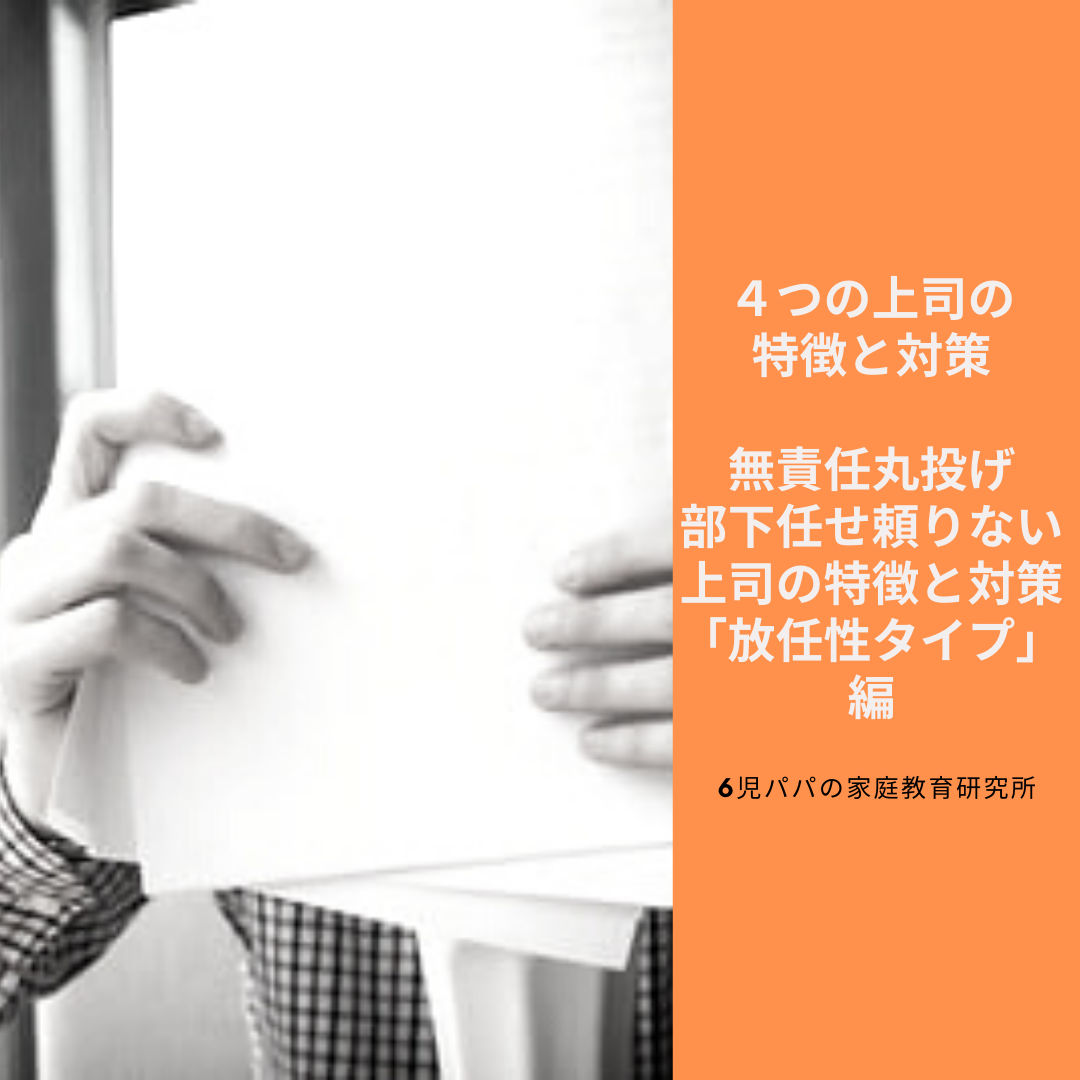


コメント